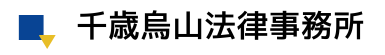はじめに
この文章は、相談者・依頼者の方向けに、相続放棄手続の理解を深めていただくため、整理したものです。
相続においては、不動産や預貯金などのプラスの財産(資産)だけでなく、借金や未払金のようなマイナスの財産(負債)も引きつぐことになっています。「負の遺産」「マイナスの相続」などと言われることもあります。
相続財産のうち、マイナスの財産(負債)のほうがプラスの財産(資産)よりも多い場合、適切に裁判所において相続放棄の手続を行うことにより、相続債務の負担からのがれられます。
なお、相続放棄の理由は問われません。相続財産が全体としてプラスであっても、個別の事情により相続したくない、相続手続に関わりたくないなどという場合に、相続放棄の手続を行うことで、相続人の地位を脱することができます。
相続放棄とは
まず、相続の基本を確認しておきます。
人が亡くなると、その瞬間に相続が開始します(民法882条)。そして、相続開始の瞬間に、亡くなった人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務が、一つのまとまりとして(包括的に)、相続人に承継されます(民法896条本文)。
※ただし、被相続人の一身に専属したものは、相続の対象となりません。
このように、相続は、相続人の認識や意向に関係なく、当然かつ包括的に生じるという原則があります。
しかし、相続される財産に借金などの多額の負債が含まれる場合や、いくら財産があっても、親族間の人間関係などを理由に相続を望まない場合もあります。そのような場合に、相続人の意思を尊重し、相続しないという選択をすることを可能にしたのが、相続放棄です。
ポイントは以下のとおり。
- 相続放棄の手続は、必ず裁判所において行う必要があります。
- 相続放棄は、相続開始前に行うことはできません。現実に相続が開始した後に行う必要があります。
- 相続放棄を行うことにより、はじめから相続人にならなかったものと扱われることになります。
相続放棄の法的効果
- 相続の放棄をした者は、その相続に関して、はじめから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
その結果、相続財産(資産及び負債)を承継することはなくなります。 - 他の共同相続人の相続分が増加します。
- 相続放棄をしたのが配偶者以外の相続人の全員である場合、後順位の相続人が相続人になります。
- なお、相続放棄した者に子や孫がいても、代襲相続は発生しません。
- なお、相続税の基礎控除額の算出においては、一部の相続人が相続放棄をしても、放棄がなかったものとみなされるため、相続放棄による不利益はありません(相続税法15条2項)。
具体的な手続
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります(民法938条)。
管轄裁判所
被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続を行います。
最後の住所地は被相続人の住民票(除票)により確認します。
具体的な管轄裁判所は、裁判所のHPで確認できます。https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html
手続の流れ
相続放棄申述申立書に必要事項を記載し、署名押印して、家庭裁判所の窓口に提出します。
必要に応じ、法定単純承認事由がないことを説明した上申書及び証拠資料も合わせて提出します。
手数料(印紙800円)、郵便切手(管轄裁判所に確認)、必要書類(戸籍、住民票など)を添付します。
必要書類の提出確認が終わると、家庭裁判所の書記官から本人(または代理人弁護士)に意思確認の照会状が送付されますので、これに回答する必要があります。
特に問題がなければ、照会状への回答後、通常2~3週間程度で申述受理の審判がなされます。
相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から本人(または代理人弁護士)に、相続放棄受理通知書が郵送され、手続は終了します。
相続放棄の際の審査内容
相続放棄手続において、裁判所が主に確認する点は、以下の3つです。
- 1 申述人が相続人であること
- 2 相続放棄の意思が真意に基づくこと
- 3 単純承認をしていないこと
① 申述人が相続人であること
提出された戸籍等の書類により相続関係が確認されます。
申述者よりも先順位の相続人がいるか(いる場合、先順位の相続人全員が相続放棄をしているか)も確認されます。同一被相続人についての先行する相続放棄申述受理手続等がある場合、既に家庭裁判所に提出済みの書類を重ねて提出する必要はありません(裁判所に確認)。
② 相続放棄の意思が真意に基づくこと
相続放棄において、特定の動機や理由は必要ありません。
他方で、相続放棄の意思が申述者本人の真意に基づくものかの確認のため、家庭裁判所の書記官から本人(または代理人弁護士)に照会状が送付されますので、これに回答する必要があります。
③ 単純承認をしていないこと
単純承認とは
無限に被相続人の権利義務を承継する(民法920条)という内容の相続人による意思表示です。
単純承認は、撤回することができません(民法919条1項)。単純承認後は、相続放棄はできなくなります。
ただ、現実には、相続人がわざわざこのような留保なしの単純承認の意思表示を行うことは通常ありません。
一方で、相続人に以下の3つの事由のいずれかがある場合、その相続人は単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。
- 法定単純承認① 相続財産の全部又は一部の処分
- 法定単純承認② 熟慮期間の経過
- 法定単純承認③ 背信的行為
法定単純承認① 相続財産の全部又は一部の処分
相続財産の処分
相続財産の売却・贈与、相続財産による弁済・相殺などの法律上の処分行為
相続財産に属する物の破壊・廃棄などの事実上の処分行為
相続財産の処分に当たるかが問題となる類型
相続債務の弁済
相続財産を用いて弁済を行った場合、相続財産の処分に当たります。
これに対し、相続人の固有の財産を用いて弁済を行った場合、相続財産の処分には当たりません。なお、自己が受取人として指定された生命保険金は、受取人(相続人)の固有の財産です。
相続開始の事実の認識がない場合
相続人が、相続開始の事実を知らずに相続財産を処分したときは、法定単純承認には該当しません(最判昭和42.4.27)。
相続財産からの葬儀費用の支出
相続債務があることを知らないまま、相続財産から葬儀費用を支出した事案において、社会的見地から不当なものではなく、法定単純承認事由である相続財産の処分には当たらないとした裁判例があります(大阪高決平成14.7.3)。ただし、あくまで個別の事情下における判断ですので、ご自身の事案にそのまま当てはまるかは、慎重な検討が必要です。
保存行為・短期賃貸借
相続人による保存行為(例:相続財産に含まれる債権の消滅時効完成を阻止するために措置)や短期賃貸借は、相続財産の処分に当たらず、法定単純承認事由にはなりません。
法定単純承認② 熟慮期間の経過
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要があります(民法915条1項本文)。この期間を「熟慮期間」と言います。
熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」が具体的にいつなのかの解釈が重要になります。(後述)
熟慮期間内に相続放棄又は限定承認をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。
熟慮期間の伸長(延長)
熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます(民法915条1項ただし書)。
法定単純承認③ 背信的行為
限定承認や相続放棄をした後でも、相続人が債権者の追求を逃れるために、以下のような背信的行為を行った場合、単純承認とみなされます。
- ⅰ 相続財産の全部または一部を隠匿
- ⅱ 相続財産の全部または一部をひそかに(「私かに」。相続債権者の不利になることを承知の上でという意味。)を消費
- ⅲ 相続財産の全部または一部を悪意で財産目録に記載しない
熟慮期間(3か月)の起算点
起算点
相続人が、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されます(民法915条1項本文)。
原則
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として、相続人が以下の2点の両方を知った時です。
- ①被相続人が死亡した事実
- ②自己がその者の相続人である事実
例外
相続人が、被相続人には相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときは,相続財産の全部又は一部の存在を認識した時または通常これを認識できるはずである時から熟慮期間(3か月)が起算されるとした最高裁判決があります(最判昭和59.4.27)。
したがって、相続財産が全くないと誤信して、相続人が相続放棄等の手続を取らなかった場合は、原則的な熟慮期間経過後に金融業者から相続債務の支払を請求されても、それから3か月以内に相続放棄を行えば、相続人としての義務を免れることができます。
では、このような例外的考慮が認められるのは、相続人が「相続財産は全く存在しない」と信じていた場合に限られるのでしょうか。近時、相続財産の存在を認識していた場合であっても、相続放棄等の具体的手続をとらなかった具体的事情を考慮して、相続債務の存在を認識した時から熟慮期間が起算されるとした裁判例が高裁レベルで相次いでいます。
いずれにせよ、相続開始後3か月を経過してからの相続放棄手続においては、個別の事情が問題とされる場合が多くなりますので、お早めに弁護士にご相談なさるのが適切です。
共同相続の場合
共同相続の場合、熟慮期間は、相続人ごとに個別に算定されます。
相続人が未成年者・成年被後見人である場合
相続人の法定代理人がその相続人のために相続の開始があったことを知った時から、熟慮期間が起算します。
再転相続の場合
被相続人(A)の相続人(B)が相続の承認も放棄もしないで死亡したとき、Bの相続人(C)(再転相続人)は、Bから第1の相続につき承認・放棄の選択をする地位も含めて相続します。このような場合を再転相続と言います。
再転相続の場合、熟慮期間は、再転相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算するとされています(民法916条)。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、再転相続人(C)が、Bからの相続により、承認・放棄の選択をする地位を含むAの相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいいます(最判令和1.8.9)。単に、Bについて、自己のために相続の開始があったことを知った時点ではありません。
相続放棄後にすべきこと
相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。
相続債権者からの督促がある場合、この相続放棄申述受理通知書のコピーを送付するなどして、相続放棄したことを知らせるとよいでしょう。
相続放棄が家庭裁判所で受理されたことの意味
家庭裁判所での相続放棄の申述の受理審判は、家庭裁判所が相続放棄の意思表示を受領する公証行為であるにとどまり、相続放棄の有効・無効を終局的に確定するものではありません。
相続放棄の有効・無効の認定は、民事訴訟による裁判によってなされることになります。
具体的には、相続債権者から相続放棄をした相続人に対し民事訴訟が提起されると、相続人は相続放棄したことを主張するのに対し、相続債権者はその無効を主張する形で相続放棄の有効性が争われ、これについて裁判所が判決において判断を下すことになります。